豊島氏滅亡悲話「照姫伝説」
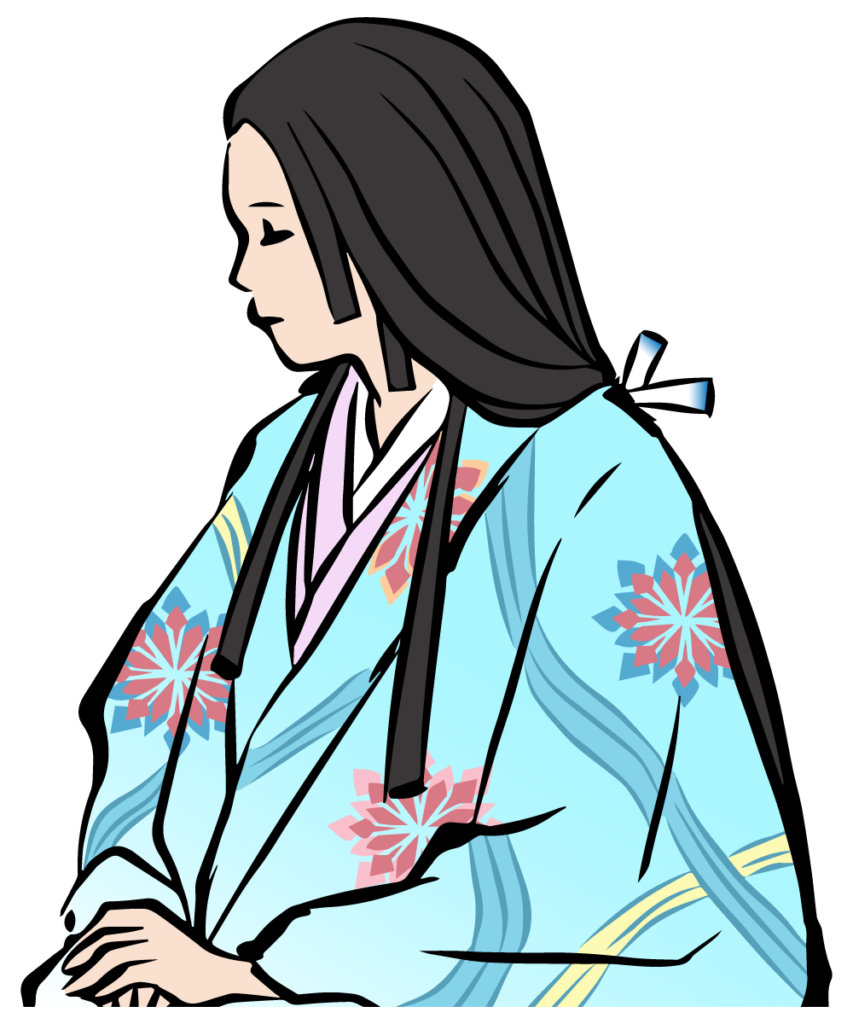
現在石神井公園では、毎年4月に照姫まつりを開催して照姫を偲んでいます。
豊島氏を題材としたお話は、この照姫を題材としたものが有名で、豊島氏の存在を世に記す貴重な伝説です。
照姫伝説

三宝寺池
室町時代の中頃の関東は、古河公方と関東管領の上杉氏が激しく対立していました。そして山内上杉家の家臣(家宰)である長尾景春が、上杉氏と対立するという混沌とした時代でした。
照姫の父豊島泰経は長尾氏側の武将で、扇内上杉家の家宰である太田道灌とは対立関係にあり、文明9年(1477年)4月についに両雄は激突します。
太田道灌は、豊島氏の城の一つ豊島城(練馬城)をまず攻略にかかります。豊島城は泰経の弟豊島泰明が城主を務める城で、対太田道灌の最前線の城でした。
道灌は豊島城周辺を焼き払った後、兵を一旦引きます。この気に豊島兄弟は道灌を追撃の兵を出しますが、江古田ケ原に兵を潜ませていた道灌に挟み撃ちにされ、泰明が討たれるという大打撃を被ります。
泰経は一旦主城である石神井城に兵を引き、籠城の構えを見せます。
しかし、道灌の猛攻の前に石神井城は陥落してしまいます。
最期を覚悟した泰経は、家宝の「金の乗鞍」を白馬に載せ崖の上に登り、道灌の兵が見守る中三宝寺池へと身を投げ最後を遂げてしまいます。
それを見ていた照姫もまた、三宝寺池へと身を投じてしまいました。
道灌は姫を憐れみ、塚を作りそこに松を植え弔いました。その松に上り三宝寺池を見下ろすと、泰経の金の乗鞍が見えるとの言い伝えがあります。
伝説誕生
この伝説はそれほど古いものではなく、明治時代に遅塚麗水が執筆した『照日の松』(明治29年(1896年)出版)という小説がベースになっています。
公卿の娘の照日姫が旅の途中の山吹の里で太田道灌と出会って、有名な七重八重の歌を交わす、照日姫は泰経の弟の泰明の妻となり、その後、道灌との合戦で泰経は敗れ、やがて、照日姫は最期を迎えるという話である。 引用:ウィキペディア
史実は石神井城陥落時には、泰経は死んでいません。泰経は平塚城にて再起をはかりますが、道灌に包囲され戦わずに兵を引きそれ以降行方不明になっています。
またこの時代は女性の系図は残っていないことが多く、照姫の実在は確認できていません。
麗水は現在で言う石神井公園を散策中に、「照日(てるひ)上人」)の塚を見て小説の原案を思いつき、照日姫と名付けたとされています。それがいつの間にか、照日姫から照姫と名前も変わってしまいました。
姫塚と殿塚
現在三宝寺池北側の公園内に、照姫の塚である「姫塚」と泰経の塚である「殿塚」があります。
「姫塚」は照姫の塚ではなく、照日上人の塚と言われていましたが、近年ではこの周辺に存在した「十三人塚」の一つではないかとの説も出ています。(十三人塚は古戦場などで死者を弔うために作られた塚)


(写真は石神井公園の姫塚とその上にある祠です。)
殿塚はさらに新しく小説が出版された後、大正年間に照姫の妹秋子の後裔を称する小谷一郎氏が造営した物です。

(石神井公園にある殿塚)
まとめ
練馬区の石神井公園では、昭和63年以来毎年4月から5月に「照姫まつり」を開催しています。
照姫の実在性より祭りによる地域振興と、この伝説から豊島氏や地域の歴史を知るきっかけになると良いですね。




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません